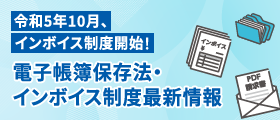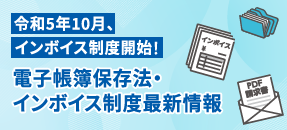税理士法人 BLUE SKYは、愛知・岐阜・三重の東海3県はもとより、東日本、西日本の幅広い企業の税務・経営をサポートしております。
中小企業から上場会社の子会社まで、業種や規模問わず、幅広い業種に対応可能です。
当社の強みは、ほとんどの顧問先企業に書面添付(税理士の責任において顧問先企業の税務・会計の信頼性を証明する書面)を実践しており、その書面添付件数は東海3県でもトップクラスです。
また、お客様と親密な関係を築き、税務・会計はもちろん、顧問先企業のパートナーとして経営課題や資金繰り・融資対応などの幅広いお悩みに対応しています。
黒字化を達成したい、よりよい会社をつくりたい方、ぜひ私たちにご相談ください。




2023.3.31 ホームページリニューアル
ホームページをリニューアルいたしました。今後とも変わらぬご愛顧を宜しくお願いいたします。